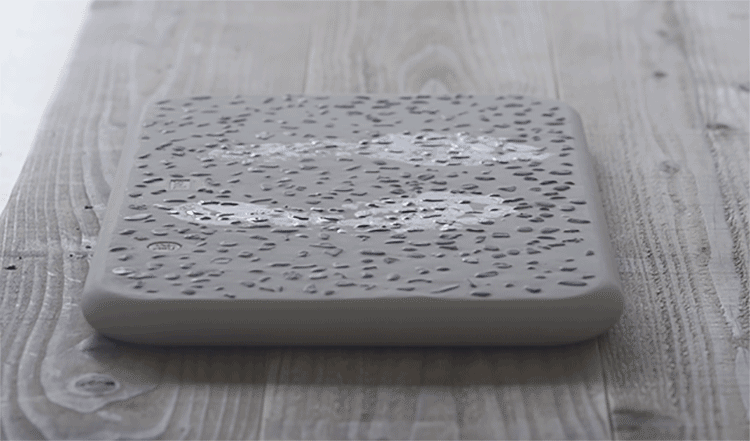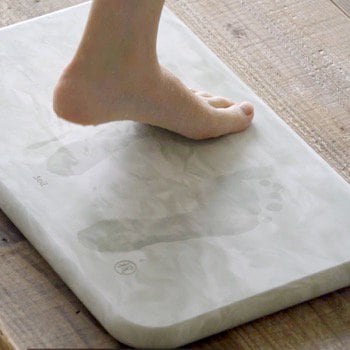【予約】soil|バスマット 梶 かき落とし【ラッピング不可】
型番:JIS-B403WH
¥16,500
165pt
数量
- 5,500円(税込)以上は国内送料当社負担
24時までのご注文で翌営業日出荷
ギフトラッピングは翌々営業日出荷
※土日・祝日は休業日
※メーカー取り寄せ商品の場合は3~5営業日出荷
※予約商品は別途ご連絡します
 ※こちらの商品は、お届けまでに約3週間前後頂き、ラッピング対応が不可となっております。 ※KONCENT web shop 限定カラーになります。実店舗では、販売しておりません。 |
|
| 製品サイズ | 約W300×D500×H30mm |
|---|---|
| 製品重量 | 約6kg |
| 対荷重 | 約80kg |
| 材質 | 秋田県産珪藻土 |
| 原産国 | 日本 |
| 備考 | ※手作りの為、模様はひとつひとつ異なります。 ※模様をお選びいただくことはできません。 |
| ブランド | soil (ソイル) |
 |
|
 |
|
こちらもおすすめ
-
¥19,800
-
¥12,100
-
¥9,900
-
¥11,000
-
¥16,500
-
¥22,000
-
¥7,480
-
¥10,450
 BATH MAT kaji
BATH MAT kaji